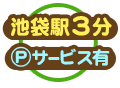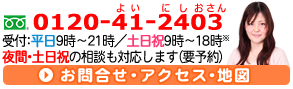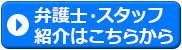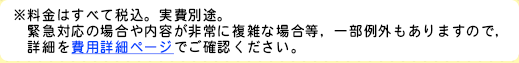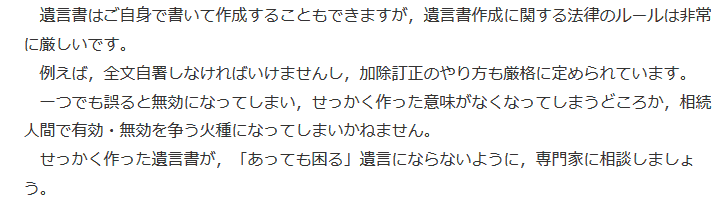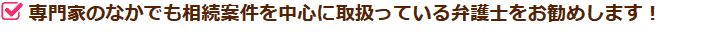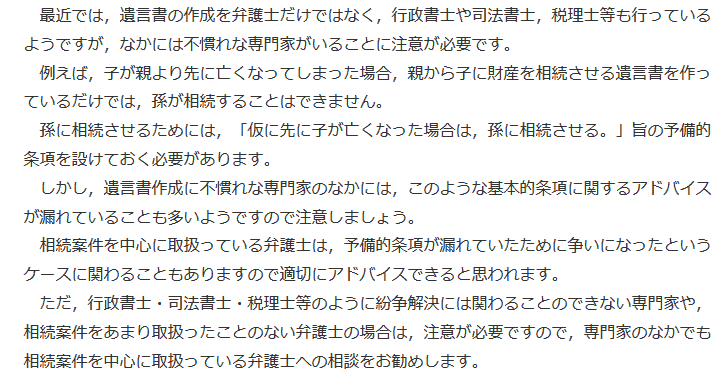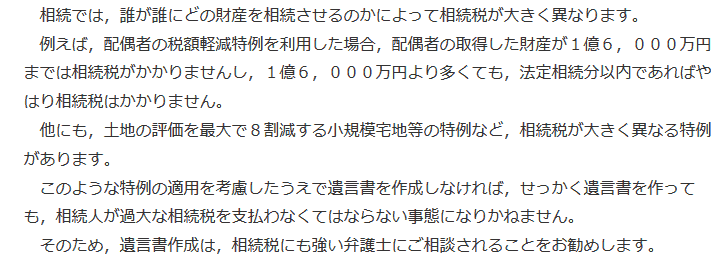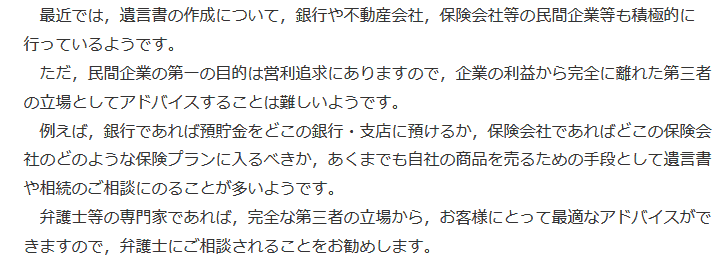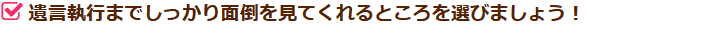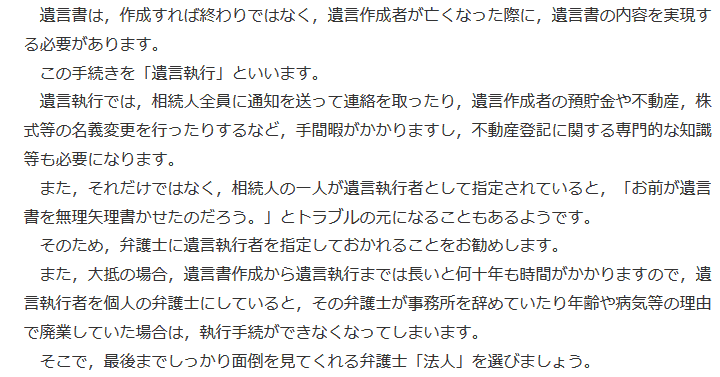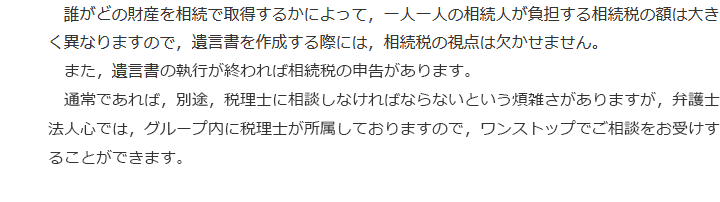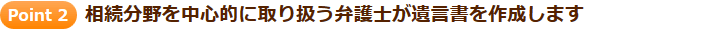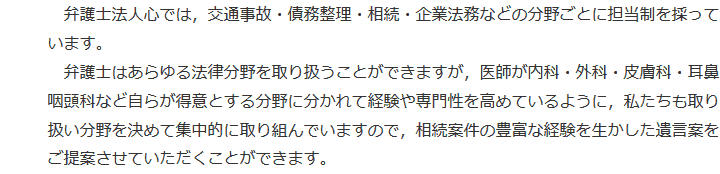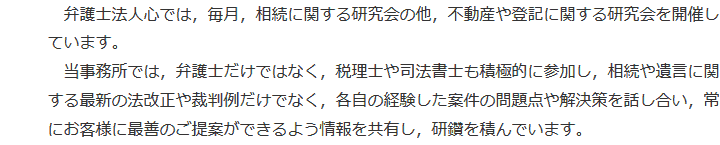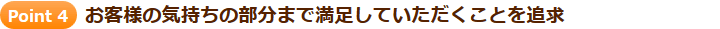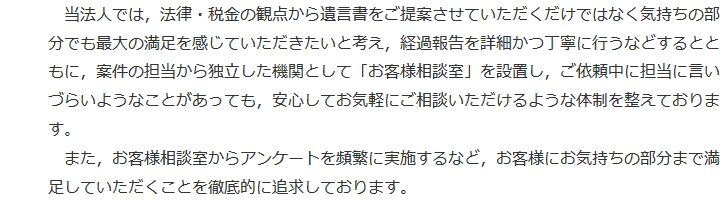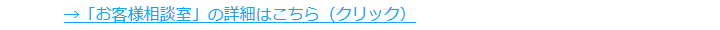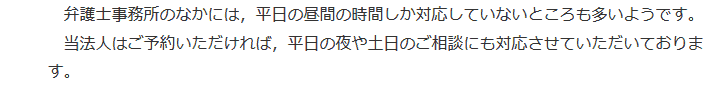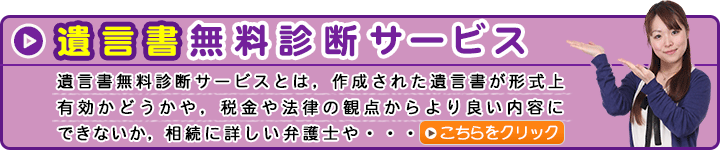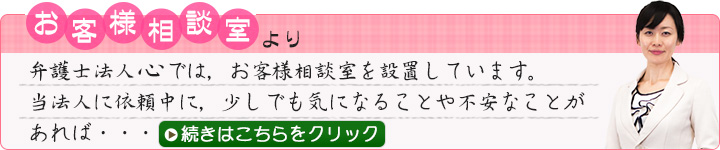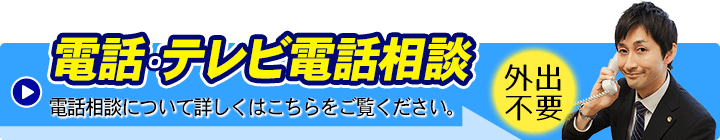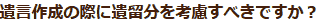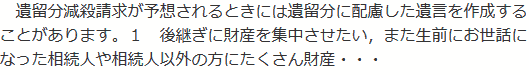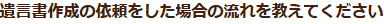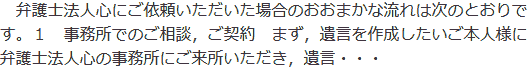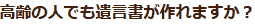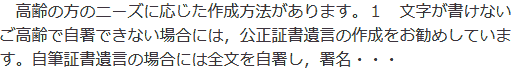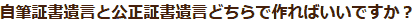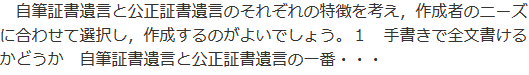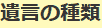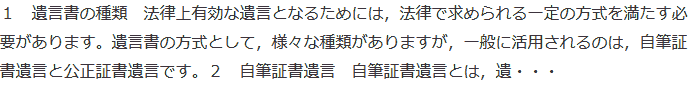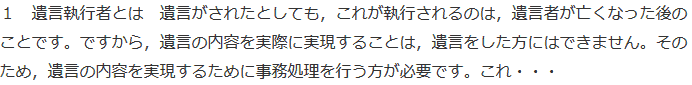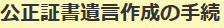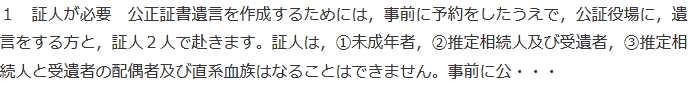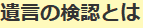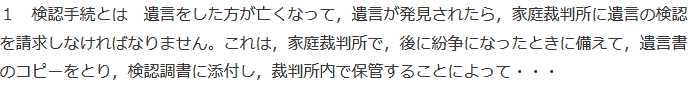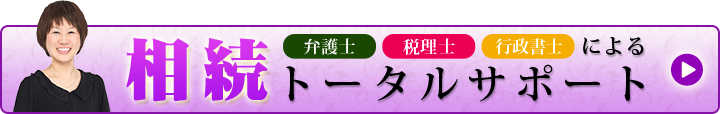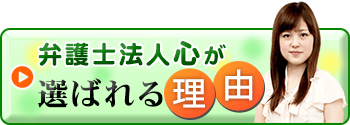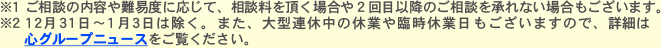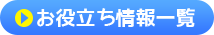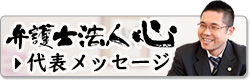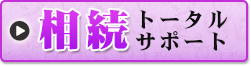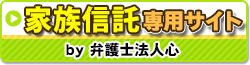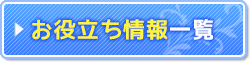遺言を作成する時に押さえておくべき基本情報
1 遺言の作成にあたっては弁護士へご相談を

遺言を作成しようと思っても、いつ作成した方がいいのか、どのような内容で作成すべきか、どの方法で遺言を作成するのがよいのか等、分からないことも多いかと思います。
遺言を作成しようと思ったら、そうお考えになったタイミングで、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 遺言を作成する時期
「自分の年齢ならまだ遺言書を作成しなくてよい」と仰る方がいますが、遺言の作成に「まだ」はありません。
いつ何が起こるかは誰にも予測はできませんし、万が一認知症等が進んでしまい、遺言能力を失ってしまうと、遺言書を作ることはできなくなってしまいます。
そのため、遺言を作成するのに時期が早すぎるということはありません。
作成できる時に作成しておき、万が一後で事情が変わった場合には、再度作成し直すことができます。
3 遺言の内容で押さえておくべきこと
⑴ 遺産の一部の遺言書は作らない
例えば、財産が不動産と預貯金がある場合でも、「自宅不動産は長女に相続させる」とだけ遺言書を書く方がいます。
遺言者になぜそのような遺言書を作成されたのかを確認すると、「長男と次女は結婚して家を出ており、長女はまだ結婚をしていないのでこの家に住み続けられるようにしたかった」とのことです。
確かに目的はわかりますが、このような遺産の一部についての遺言書は、かえって混乱を招くことになります。
例えば、長女が相続する不動産の価値が5000万円、預貯金が1億円の場合、預貯金はどのように分けるのでしょうか?
一般的には、一部遺言の場合は、特別受益と同様に考えますので、長女は不動産のみを相続し、長男と次女が5000万円ずつ預金を分け合うと考えられます。
しかし、「特別受益のもち戻し免除」の意思表示があったと考えられる場合には、長女が不動産+3333万3333円、長男と次女が3333万3333円ずつという解釈もありえます。
遺言者の意思がどちらであったかは、遺言書から読み取れませんので、争わないために遺言書を作成したはずなのに、かえって紛争を誘発してしまうことになりかねません。
別の例として、複数の不動産と預貯金があり、ABC3人の子がいるケースで、「Aに不動産Xを、Bに不動産Yを相続させる」と書いてあるものの、預貯金について言及が無い場合には、より大きな混乱を招くことになります。
Cがいくら預貯金を取得するのかの問題の他に、AとBの不動産の差について、預貯金で調整を図るのか、図らないのかで、争いが生じることもあるからです。
⑵ 遺留分について検討をしておく
相続人には、兄弟相続の場合を除き、遺留分という最低限の権利が存在します。
遺留分を無視して相続人の一人にすべての遺産を相続させる等の遺言をすることは自由ですが、他の相続人が遺留分を請求する可能性は念頭に置いて、対策をしておく必要があります。
例えば、家業に用いている不動産2憶円を、家業を引き継ぐ長男に相続させるために、「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成したとします。
しかし、預貯金が2000万円しかなかったとすると、もう一人の相続人である次男から遺留分侵害額請求を受けた際、遺留分(5500万円)を預金から支払うことができませんので、不動産を売却して支払わざるをえなくなれば、結局家業も廃業になってしまいます。
遺留分に備え、遺留分を満たす分の生命保険金を準備するとか、不動産の一部を売却するために分筆をしておくとか、場合によっては法人化と株式譲渡を検討するなど、手を打つ必要があります。
⑶ 内容はわかりやすくはっきりと書く
複数の解釈ができてしまう等、あいまいな内容の遺言書は争いのもとです。
帰属方法を指定したのか、分割方法を指定したのかで、法的効力は大きく異なります。
不動産についても登記ができなければ意味がありません。
「~~市の不動産」「~にある山林〇〇平方メートル」では登記ができず、結局相続人全員の実印が必要になってしまうことがよくあります。
4 遺言の種類
特殊な遺言を除き、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。
それぞれ、特徴やメリットがありますので、ご自身の状況に合った方法で作成されるのがよいかと思います。
⑴ 公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が読み上げ、遺言者の他、公証人と証人2人が間違いのないことを確認して作成されるものですから、作成過程が担保されており、無効になりにくい遺言書です。
また、自筆証書遺言とは異なり、公証役場で保存されますので、公正証書遺言を残した旨を相続人に伝えておけば、遺言が発見できないというケースはまずありません。将来遺言の効力が争われる可能性がある場合等は確実性のより高い公正証書遺言を作成しておくことが望ましいです。
⑵ 自筆証書遺言
自筆証書遺言は原則として全文を自筆し、日付、署名捺印をすることで作成する遺言書です。
遺言者本人が書いたものなのかどうかや、遺言能力の有無、内容の解釈等により争いが生じやすい遺言書ですので、専門家に相談して作成することが重要です。
また、自筆証書遺言の場合には、保管についても注意が必要です。
自宅に保管される方も多いかと思いますが、誰かに見られてしまう可能性や、反対に遺言書を発見できないという問題が生じることもあります。
なお、後述で詳しく説明しますが、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度もあります。
5 遺言書に関する相続法改正
自筆証書遺言に関して、令和元年7月に40年ぶりに大きな改正が行われました。
大きな改正点は以下の2つです。
⑴ 全文自筆の緩和
今までは遺言書の全文を自筆で作成する必要がありましたが、今回の法改正で、財産目録についてはPC等で作成することが可能になりました。
特に、これまでは不動産について登記簿どおりに情報を記載するために、かなりの文字数を自筆で記載しなければなりませんでしたが、この改正により、自筆証書遺言が作成しやすくなることが期待されます。
注意する点としては、PC等で作成することができるようになった財産目録についても、「全てのページに署名捺印」をする必要があることです。
自筆証書遺言は形式要件が厳しく、欠けると無効になってしまいますので、注意しましょう。
⑵ 自筆証書遺言を法務局で保管する制度
新法から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
遺筆証書遺言は、遺言者が本人かどうかや、偽造、変造等を理由として争いになりやすいというデメリットがありましたが、本人確認をしたうえで法務局が預かるという本制度を利用することで、自筆証書遺言をめぐるトラブルが減ることになります。
また、この制度を利用し、法務局が預かった自筆証書遺言については、検認が不要になります。
自筆証書遺言のデメリットの1つであった、家庭裁判所への検認手続が必要であり、相続人にとって手間となるという点も解消されたため、自筆証書遺言を利用しやすくなりました。
6 遺言の作成をお考えの方へ
公正証書遺言を作成すべきか、自筆証書遺言を作成すべきかという悩みは、本改正で自筆証書遺言の制度が改良されたことで、より難しくなったという側面もあります。
どちらの方法で作成するのがよいかは、それぞれの状況によって変わってきます。
遺言書の内容やご家族の状況をふまえ、最善の遺言書を作成するためには、遺言を得意とする弁護士にご相談ください。